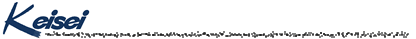
先月何気なく皇居の堀端を歩く機会がありました。歴史の「江戸城無血開城」をふと思い出し、江戸城の初期はどのような風景があったのか。その時代の人は今の東京がどのように見えるのかと。
今回は「江戸城」に付いて調べてみました。
古くは十二世紀初頭、秩父平氏である秩父重綱の四男・重継がこの地に館を構えたという。
康正二(1456)年、扇谷上杉家家老・太田道灌が上杉定正の命で築城し翌長録元(1457)年四月八日に完成した。
江戸城、岩槻城、川越城をもって、古河公方・足利成氏に対抗した。長禄元(1457)年に完成した。築城当時は複数の曲輪を持つ斬新な城と言われたが、現在残るほどの規模ではなく、掻き揚げ土塁の城であった。
「静勝軒」と呼ばれる三階建ての初期天守の原型となる櫓を持っていた。
文明九(1479)年、長尾景春の乱に乗じて石神井城の豊島泰経らが挙兵し、川越城と江戸城の連絡を遮断した。太田道灌は四月、扇谷上杉朝昌、相模新井城主・三浦氏、武蔵赤塚城主・千葉自胤、世田谷城主・吉良成高らの援兵で江戸城防備を固め、豊島泰経の弟・泰高の平塚城を攻めた。泰経は石神井城・練馬城から援兵を出し、太田・豊島両軍は江古田原・沼袋原で合戦となった(江古田・沼袋合戦)。泰明は討ち死にし、泰経は石神井城に立て籠もったが、四月二十八日に落城した。
太田道灌は主家を上回る名声に危機感を抱いた扇谷上杉定正により、文明十八(1486)年、相模糟屋の上杉館で斬殺され、江戸城には曾我豊後守を城代として置き、その後永正二(1505)年、定正の養子、朝良が居城とした。
大永四(1524)年正月、小田原城の北条氏綱は武蔵に兵を進め、扇谷上杉朝興と高輪原で対陣した(高輪原合戦)が、その際に江戸城代・太田資高の内応を得て江戸城奪取に成功、以降、北条氏の城代、遠山氏、富永氏が置かれ、武蔵・下総への進出拠点となった。
天正十八(1590)年の小田原の役の際は川村秀重が守備していたが、四月二十二日に徳川軍に降伏開城した。
北条氏が滅亡すると、同年八月一日、秀吉の命により徳川家康が駿府城から江戸城に入り、関東一円を領土とした。
家康は文禄元(1592)年頃から西の丸を中心に普請を開始、また城下の日比谷入江の干拓など、城下町の整備にも着手した。
慶長五(1600)年の関ヶ原合戦勝利後、家康は慶長八(1603)年に征夷大将軍に任じられ、江戸に幕府を開いた。これにより、慶長九(1604)年に江戸城の普請を全国大名に発令、藤堂高虎らに縄張りをさせて慶長十一(1606)年三月一日を起工日として、外様大名を中心とした諸大名に命じて天下普請による大改修を行い、寛永十三(1636)年、三代家光の時代に完成した。
家康・秀忠・家光の時代にそれぞれ天守が造営され、家光の時代の天守は寛永十四(1637)年十二月六日に竣工したが、明暦三(1657)年正月十八日の江戸の大火(「振袖火事」)で天守は焼失し以後再建されなかった。
慶応三(1867)年十月、第十五代将軍徳川慶喜は二条城にて大政奉還を上表、江戸城は翌慶応四(1868・明治に改元)年三月十四日、倒幕派による総攻撃の前夜に攻撃中止が命令され、四月十一日、無血開城した。
明治元(1868)年十月十三日、明治天皇は京都から江戸城に入り、「東京城」と改めた。現在は皇居。
ケイポール製品の詳細に付いては「ケイポール商品」で御覧ください。
このコーナーのご意見・評論はrun@k-pole.co.jp までヨロシク!