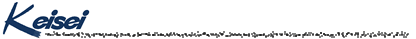
暑い夏も秋の気配が感じられる時期になってきました。
本格的に腰を据えてお酒の呑む機会が多くなる人も大勢いらっしゃるでしょう。
そんな皆様の為に、お酒の本質・呑み方・付き合い方を少し。
「余計な事」と言わないで読んでください。
お酒は「百薬之長」ではない
われわれの文化はアルコールの使用をもてはやし、ときには適度のアルコールははからだにいいと言われてきた。
しかし、日本人は世界でもまれに見るほど、お酒に弱く、呑み方の下手くそな民族ですので、一生からだに何の影響もなく、むしろ寿命を延ばすのに意義のある呑み方ができるようになるには、大変な修行がいるものです。したがって、 まず普通の人にとっては、お酒は百薬之長ではないと思うべきでしょう。
最近では、アルコール依存症、アルコール中毒、アルコール性痴呆の人が増えています。また、ドック検診で見つかるアルコール性の肝障害や高γ-GTP血症や脂肪肝の人が増えており、受診者の6割を超えているという報告があります。
また、いくらまでだったらアルコールを呑んでもよいという基準は本来ないものです(「危険の最も少ない飲酒」として、1日平均1合程度である、と「健康日本21」で唱われているが、これは非常に問題である)。一生にわたって、健康に呑みつづけられる飲酒量は、人それぞれで違うもの。このような平均の数値(集団の値)を個人に当てはめないことが肝腎である。人によっては、肝臓が悪くなっていてもそのぐらいだったら問題ないと勝手に判断してしまうから用心すること。
お酒はコントロールして上手に呑もう
● コントロールするとは、「呑まないでおこうと思ったら、いつでも呑まないで おれる」という範囲内で呑むということ。
● 理想的には、呑まないことが通常の生活で、ときに「自分をなぐさめる」とき、友人と 「語らう」ときなどに、潤滑油として適量呑むという生活態度が望まれる。
●「休肝日」を作ることが、一部で唱道されているが、これはストレスだけがかかるだけ(飲酒量はそれ程少なくならない?)。
● アルコールの危険から身を守る最良の方法は、毎日呑むという習慣をやめること。 お酒を呑む多くの人は、毎日呑むものだと信じている。からだにはお酒はとくに必要なものではない。毎日呑むものではないという前提で、呑み方を工夫することが大事。
● アルコールをリラクセーションの手段として使わないこと。その他のリラクセーションの方法のどれかを使ってリラックスする習慣を身につけることが肝腎である。
● 肝臓・泌尿器・前立腺に問題がある人、上部消化管(食道、胃、十二指腸)に潰瘍がある人、精神神経系に問題がある人は、絶対にアルコールを呑んではならない。
● アルコールにはカロリーがある。炭水化物のそれに似ているが、からだはそのエネルギーを蓄積できず、その場で燃焼させなければならない。したがって、アルコールと同時に摂取した食物のカロリーは脂肪に変わりやすく、からだに蓄積されることになる。
● アルコール依存だという人は断酒会に応援を求めるか、カウンセラーに相談すること。
助けを求めるまでに、何とかしましょう。自身の体の為、家族の為ですよ。
ケイポール製品の詳細に付いては「ケイポール商品」で御覧ください。
このコーナーのご意見・評論はrun@k-pole.co.jp までヨロシク!