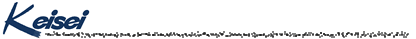第二話 1998.11.25
早いものですね。今年も後一ヶ月ほどとなりました。
年末に向けて何かと仕事が増え、猫の手も借りたくなるくらいな毎日を送り、一度に複数の事項を処理できればいいなと、思ってらっしゃる貴方に。今回はそれを実行された方の話です。
「聖徳太子」 用明天皇の皇子にして飛鳥時代、真の主導者・大政治家である。
母の穴穂部間人皇后(あなほべのはしひと)が、宮廷を歩いていた時、たまたま厩戸の前で太子が生まれたので、別名を厩戸豊聡耳皇子(うまやどのとよとみみ)とか、上宮皇子とも言う。
この厩戸の名の由来として、キリストが厩で生まれた話に似ている事に注目し、唐の都の長安でおこなわれていたキリスト教の知識を、大唐学問僧が日本に持ちかえり、太子誕生説話に用いたものであろうと言う、説による。
又、上宮皇子とは、父の用明天皇が住む宮の近くの上宮に住んでいた事にもとづいている。
「聖徳太子」19才のとき(593年)推古女帝の皇太子となり、次期皇位継承者であるが、この時期、蘇我馬子が大連の物部氏を滅ぼし、さらに崇峻天皇を殺し、権力をふるっていた為、天皇家に危機が迫っていた。
その為国政を担当する任務を負かされたのである。
そしてだれもが知る日本史上有名なるあの、冠位十二階を制定し、憲法十七条も続いて制定したのである。
聖徳太子の逸話に、「同時に数人の話を聞き、適切な指示を即座にした」とされている。
この話にも説明出来る推論がある。それは太子には優秀な三人の側近がいた。
一人目が仏教の師、高句麗の慧慈
二人目が儒教の師、百済系と思われる覚哿
三人目が新羅系渡来氏族である秦河勝
三人の側近は東アジアの国際情勢について、太子に説明していた。
この側近により、独自の外交、内政を展開していったのであろう。
この話は西暦600年時代の事柄ではあるが、時代が現代なっても十分通じる話だと痛切に感じる。
今の政治に改めて登場願いたいと考えるのは小生だけだろうか。
国だけでなく、成功・失敗をした全ての要因に上げられるのではないか。
小さくても、クラブ・団体・会社等人事に付いても要注意!
![]()
最後に「聖徳太子」の「憲法十七条」(道徳規範)内容は一般にはあまり知られていないので次に示します。
十七条憲法・主文
第 一 条 和をもって貴しとなし、忤うることなきを宗とせよ (調和・協力の精神)
第 二 条 篤く三宝を敬え (仏教への尊崇)
第 三 条 詔を承りては、かならず謹め (忠君の精神)
第 四 条 群卿百寮、礼をもって本とせよ (礼節の精神)
第 五 条 餐を絶ち、欲を棄てて、明らかに訴訟を弁えよ (贈収賄の禁止)
第 六 条 人の善を匿すことなく、悪を見てはかならず匡せ (勧善懲悪)
第 七 条 人各任あり。掌ること宜しく濫れざるべし (職権乱用の禁止)
第 八 条 群卿百寮、早く朝り晏く退でよ (遅刻・早退の禁止)
第 九 条 信は是れ、義の本なり、事毎に信あれ (誠実の精神)
第 十 条 忿の絶ち、瞋を棄てて、人の違うを怒らざれ (叱責の禁止)
第十一条 功過を明察にして、賞罰かならず当てよ (信賞必罰)
第十二条 国司、国造、百姓に斂めることなかれ (地方官の私税禁止)
第十三条 諸々の任させる官者、同じく職掌を知れ (職務怠慢の禁止)
第十四条 群臣百寮、嫉妬あることなかれ (嫉妬の禁止)
第十五条 私を背きて、公に向くは、是れ臣の道なり (滅私奉公)
第十六条 民を使うに時をもってするは、古の良典なり (農繁期の労役の禁止)
第十七条 大事を独り断むべからず (独断専行の禁止)
今の議員さんの為に国会議事堂内に張り出そうか。
以上新たな事柄につづく
引用(万有百科日本史より)
ケイポール製品の詳細に付いては「ケイポール商品」で御覧ください。
このコーナーのご意見・評論はrun@k-pole.co.jp までヨロシク!