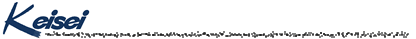
20世紀から21世紀になり、浮かれてた年末年始。
早一ヶ月がたち、一番寒い月を迎える何と時間の進むのが早い事か!。
21世紀、1000年毎に全て御破算からのスタートとは行きませんよね。
つらい日々がまだまだ続くのみです。
21世紀、どのような世の中になるのでしょうか。「下馬評」によると全体はやや良好、良い企業と、悪い企業のどちらか、真ん中が無いと言う事だそうです。
こんな時に「下馬評」の使い方は違うでしょうが、今回の話の前振りで使用しました。
で、ご存知てすよね、でもこの言葉の意味て知ってます。
今回は良く知っている・良く使うけど、「その意味は」で「なんだろう」と言う言葉を少しですが集めて見ました。いくつご存知ですか?。
将棋の「歩」の裏はなぜ「と」なの?
実は、「と」いう文字は「金」のくずし文字なのです。
正確には「と」ではなく、きわめて「と」ににているのです。 カタカナで「ト」と書かれているのは明らかに誤りです。
「サボる」
これは、フランス語の「サボタージュ」を略して動詞化したことばだと言われています。 昔、サボ(木靴)を作る職人の中に、酒好きのものや怠け者が多くいたそうで、相当雇い主を困らせて いたと言われます。そんなことから「木靴製造」という意味のサボタージュを借用して怠け仕事の 意味に用いられているみたいです。
「ろれつ」が回らない。
この「ろれつ」は漢字の"呂律"が訛ったことばだといわれています。
呂律の"呂"と"律"は、中国の古代音楽の音調が伝わってきたもので、日本では雅楽などで 使われている音楽の調子のことです。 昔、曲を奏でた時に、この呂と律の音階がうまく合わないことを、呂律が回らないといいました。 その後、解釈が変わって、酔った人や幼児のしゃべり方がはっきりしないことを指すようになりました。
「徳利」 この「徳利」の語源はいくつかありますが、そのひとつは、この器で飲んだほうが「徳となる」 「利となる」というわけで徳利というようになった説。
又は、その口から酒が出る時 「トクトク」という音がすることから徳利となった説。また豊臣秀吉が戦利品として持ち帰った 朝鮮の酒壺が、朝鮮では「トックール」と呼ばれていたので徳利といわれるようになった という説があります。
「 くだらない」
「くだらない」という語源説に酒が関係しているものがあるのです。
清酒は昔から上方が本場とされ、この本場の酒が東海道を下って江戸へ運ばれてきたので、 これを「下り酒」と呼びました。これに対して、関東で作られていた地酒は原料や米の水質が劣り、 味が一段落ちるので「下らぬ酒」はまずい酒の代名詞となり、やがて取るに足りないなどを 意味する「くだらない」ということばができたといわれています。
なんで「親知らず」?
小学校の低学年頃にはだいたい永久歯が生え揃うが、臼歯(親知らず)は15〜16歳 に生えてくる。しかし、これは現代人の平均であり、昔の人は20歳前後だったという。 昔は人生50年という時もあり、20歳ころには親が亡くなっていることが多く、 そこから「親知らず」と呼ばれるようになったという。
「散歩」の語源
3、4世紀ころの中国では、麻薬的な五石散という薬があったそうです。 五石散には硫黄・白石英などの鉱物が入っていて虚弱体質を治す妙薬といわれていたそうです。 そしてこの薬を飲むと体がポカポカしてくる状態を「散発」と言っていました。 「散発」があらわれないと死に至る場合があり、「散発」を早めるために当時の人は歩きまわったそうです。 ここから「散歩」という言葉が生まれたのです。
「てんやわんや」
「てんでばらばら」の「てんで」と、「むちゃくちゃ」という意の関西弁「わや」が結び付いて できたという説があります。「てんで」は「手に手に」の変化したものといわれています。 広く使われるようになったのは、江戸時代からで獅子文六の小説「てんやわんや」が世に出てからと 言われています。
「手ぐすねをひく」
漢字では「手薬練ひく」と書き、武士が手のひらに薬練(くすね)を塗ることを意味します。 薬練は松脂(まつやに)を油で煮て練ったもので、弓弦や糸を強くするために用いました。 また、矢を射たときの衝撃で、弓が手のひらから飛び出さないように、左手にも塗ったのです。 そこから、薬練を引いて、すっかり準備万端整えて、機会を待つことを「手ぐすねをひく」と いうようになったのです。
「 ごまかす」
いろいろな説があるようですが、「胡麻菓子」語源説を紹介しましょう。
見かけはゴマがついていていかにもおいしそうだが、実はまずい菓子のことを「胡麻菓子」と いったことから、「だます」事を「ごまかす」というようになったそうです。
手塩にかける 「手塩」とは、
塩を盛った皿のことで、昔、食膳に置いて、膳の不浄を清めるとともに、各自の好みで 料理の塩かげんをしたのです。つまり、自分の手にかけてあれこれ面倒をみることを意味するのです。 おあいそ 実はこのことば、最初は店の人が勘定書きを客に渡すときに使ったものなのです。
歌舞伎のなかで「愛想尽かしをする」という、
本心とは裏腹に男と縁を切ることを意味する言葉が あるのですが、そこからきたという説があります。 また、勘定書きを出すとお客がいやがって愛想を尽かすことから「おあいそ」というようになった説も あります。
「OK」の語源
雑学の帝王情報 all correct(全て正しい)を all korrect と間違えて書いたことから O.K. となった・・・。その後、O.K.Club というクラブで、1840年に大統領の再選運動が行われ、標語として使われたことから、一般に広まったそうです。
虎の巻 「虎の巻」という言葉は、
いまから約二千五百年前、中国の周という国の太公望が著した 「りくとう」という戦争の本からとられたものなのです。 この「りくとう」は、文・武・龍・虎・豹・犬の全6巻からなっていますが、この中の第4巻の虎が もっともむずかしい秘伝とされていたところから、「虎の巻」という言葉がうまれたのです。
最終ランナーはなぜ「アンカー」
これはもともと綱引き競技で使われた言葉なのです。 綱を引っぱる最後尾に体重の一番重い選手を置き、錨(アンカー)の役目をさせて引きずられないように したのです。この最後尾の人をアンカーと呼び、リレー競技などにも使われるようになったのです。
イカはなぜ「いっぱい」「にはい」と数える?
イカは昔、胴だけを食べていたことからきたのです。 イカの胴は水をすくうのにちょうどいい形をしているので「いっぱい」「にはい」と数えるように なったのです。カニ・スッポンなども同様の理由で同じように数えます。 マグロやカツオは胴が丸いので1本2本、カレイやヒラメはうすっぺらいので1枚2枚です。
「下馬評」
専門家ではない人たちの評価という意味で使われるが、この語源は、入城した大名を待っている 所(下馬先)でお供たちがしているうわさ話からきています。
皆様このコーナーの下馬評はどの様な物でしょうか?。気になる所でありますが。
(参考文献 語源雑学より)
ケイポール製品の詳細に付いては「ケイポール商品」で御覧ください。
このコーナーのご意見・評論はrun@k-pole.co.jp までヨロシク!